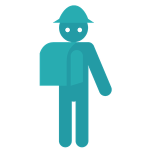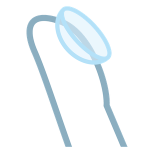【質問】コロナ治療薬について教えてください。 『発症8日目、
【A】質問者の記載にもありますが、酸素療法が必要ではない患者に対して、発症8日目以降で使用できる抗ウイルス薬は現在のところありません。酸素を必要する患者で中等症Ⅱ以上の患者に対してはバリシチニブ(オルミエント)などが検討されます。バリシチニブ(オルミエント)は最長14日間となります。新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き第10版を参考にしました。
ラゲブリオカプセル200mg ‥ 症状発現から5日以内
SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。臨床試験において、症状発現から 6 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏づけるデータは得られていない。
パキロビッドパック‥ 症状発現から5日以内
SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること.臨床 試験において,症状発現から 6 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏づけるデータは得られていない]
ゾコーバ錠 125 mg‥ 症状発現から3日以内
本剤の有効性は症状発現から 3 日目までに投与開始された患者において推定されており, SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから遅くとも 72 時間以内に初回投与すること.
ベクルリー点滴静注用 100 mg‥ 症状発現から3日以内
SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始し,3 日目まで投与する.ただし,SARS-CoV-2 による肺炎を有する患者では,目安として,5 日目まで 投与し,症状の改善が認められない場合には 10 日目まで投与する.
(各社添付文書
新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き第10版 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/kansensyo/other/covid-19/iryoukikan.data/tebiki10.pdf)
当患者には使用でいないが、酸素を必要する患者に対しては、デキサメタゾンの使用が考慮され、それでも改善しない場合はバリシチニブ(オルミエント)が使用できる。バリシチニブ(オルミエント)の使用は最長14日以内となる。