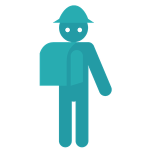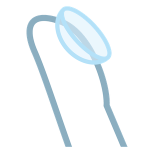【A】海外では生ワクチンも不活化ワクチンも同時であれば摂取可能である。日本では厚生労働省定期接種実施要領や各ワクチンの添付文書の中で「2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチンを使用する場合を除く)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。」と記載されており、原則1本だけとなっている。日本小児科学会は「ワクチンの同時接種は、日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気から守るために必要な医療行為であると考える。」と明記している。
日本においてはワクチンの同時摂取は原則1本のみとなっているが、海外の例や日本小児科学会を参考に、一度に2種類以上の同時摂取が可能と考えられる。ただし、ワクチンの同時摂取は以下の詳細を参考に施設の医療担当者の裁量と判断となる。
複数のワクチンを1 つのシリンジに混ぜて接種しないことに注意が必要である。
「日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気(VPD)から確実に守るためには、必要なワクチンを適切な時期に適切な回数接種することが重要である。そのためには、日本国内において、同時接種をより一般的な医療行為として行っていく必要がある。」
「ワクチンの同時接種は、日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気から守るために必要な医療行為であると考える。」
(日本小児科学会)
https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=47
米国
- 生ワクチンと生ワクチンは同時摂取しなければ、27日以上の間隔をあける必要がある。
- 不活化ワクチンと不活化ワクチンは「同時」または「いかなる間隔」でも摂取可能。
- 不活化ワクチンと生ワクチンは「同時」または「いかなる間隔」でも摂取可能。
生ワクチン‥弱毒化したウイルスを投与
不活化ワクチン‥抗原物質のみ投与
生ワクチン‥麻疹、風疹、ムンプス、水痘、BCG、ロタ(ロタリックス/ロタリック)、OPV (経口生ポリオ)
不活化ワクチン‥DPT(ジフテリアと破傷風)、Hib (アクトヒブ)、PCV-7/13 (プレベナー・小児用肺炎球菌)、日本脳炎 (ジェービック・エンセパック)、IPV(不活化ポリオ)、インフルエンザ、HBV(ビームゲン)、HAV(エイムゲン)、PSV-23(ニューモバックス・肺炎球菌)、HPV(サーバリックス/ガータジル・ヒトパピローマウイルス)、狂犬病ワクチン
摂取部位
生ワクチン‥皮下注が原則
不活化ワクチン‥筋注が原則
摂取回数
生ワクチン‥理論上は1回
不活化ワクチン‥複数回
日本におけるワクチンの投与間隔
同時摂取‥原則1本だけ
不活化ワクチン→不活化ワクチンor生ワクチン ‥7日間あける
生ワクチン→不活化ワクチンor生ワクチン‥28日間あける
【同時接種】 あらかじめ混合されていない2種類以上のワクチンを、別々の注射器や器具を用いて、同一の対象者に対して一度の受診機会に接種すること。
「2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチンを使用する場合を除く)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。」 (厚生労働省定期接種実施要領)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000036493.html
他のワクチン製剤との接種間隔 生ワクチンの接種を受けた者は, 通常, 27日以上, また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は, 通常, 6日以上間隔をおいて本剤を接種すること。ただし, 医師が必要と認めた場合 には,同時に接種することができるなお,本剤を他のワク チンと混合して接種してはならない (各ワクチン製剤の添付文書)
「日本小児科学会は、ワクチンの同時接種は、日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気から守るために必要な医療行為であると考える。」
(日本小児科学会2011.1.19登録、2011.4.27更新)
https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=47
1) 複数のワクチン(生ワクチンを含む)を同時に接種して、それぞれのワクチンに対する有効性について、お互いのワクチンによる干渉はない。
2) 複数のワクチン(生ワクチンを含む)を同時に接種して、それぞれのワクチンの有害事象、副反応の頻度が上がることはない。
3) 同時接種において、接種できるワクチン(生ワクチンを含む)の本数に原則制限はない。
(日本小児科学会)
https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=47
同時接種を行う際、以下の点について留意する必要がある。
①複数のワクチンを1 つのシリンジに混ぜて接種しない(シリンジ:注射器)。 ②皮下接種部位の候補場所として、上腕外側ならびに大腿前外側があげられる。 ③上腕ならびに大腿の同側の近い部位に接種する際、接種部位の局所反応が出た場合に重ならないように、少なくとも2.5cm 以上あける。(一般社団法人日本ワクチン産業協会 予防接種に関するQ&A集2017(平成29年))
http://www.wakutin.or.jp/medical/