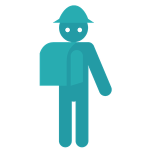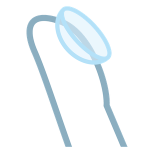【質問】ユニフィルによる夜間頻尿が考えられる場合、朝食後投与を考慮してもよいか。それとも、処方の変更が望ましいか。
【回答】
テオフィリンは気管支拡張薬として有効である一方、腎臓でのアデノシンA1受容体遮断により尿量を増加させ、中枢神経刺激で睡眠を浅くする作用があります。これらが夜間頻尿の原因となることがあります。
対策としては服薬タイミングの変更(朝食後への変更や分割投与)が考えられますが、夜間の気道収縮に対する効果減弱に注意が必要です。
LAMA・LABA・ICSなどの全身作用の少ない吸入薬への切り替えが推奨されます。これらは夜間頻尿のリスクが低く、特に高齢者や合併症のある患者に適しています。
テオフィリンの作用機序と夜間頻尿の関係
ユニフィル(テオフィリン)は主にホスホジエステラーゼ阻害とアデノシン受容体拮抗により気管支平滑筋を弛緩させることで、「気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫」に効果があります。添付文書上の適用も「気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫」のみです。しかし、テオフィリンは気管支平滑筋を弛緩以外にも作用があり、例えば、腎臓でのアデノシンA1受容体遮断により腎血流や糸球体濾過が増加し、尿量が増える作用があります。また、テオフィリンは中枢神経系も刺激するため、睡眠を浅くする効果もあります。これらの作用により、特に夕方や就寝前に服用すると、就寝中に尿が多く生成されて膀胱に尿が蓄積し、さらに睡眠が浅いため目覚めてしまい、夜間頻尿を引き起こす可能性があります。添付文書にも副作用として「頻尿と不眠」が記載されています。
夜間頻尿への対策
夜間頻尿への対策として服薬タイミングの変更は選択肢の一つです。添付文書は下記の理由により「夕食後1日1回」と設定されていると考えられます。
- 喘息やCOPDなどの呼吸器疾患では、夜間〜明け方にかけて気道が収縮しやすく、症状(咳、喘鳴、呼吸困難)が悪化しやすい傾向がある
- 夕食後にテオフィリンを服用すると、薬の吸収とともに夜〜翌朝にかけて有効血中濃度を維持しやすくなるため、夜間悪化の予防となる。
実際、テオフィリン徐放製剤を朝投与と夕投与で比較した研究では、どちらの投与でも血中濃度や効果に大差はないものの、夕方投与の方が夜間症状のコントロールに有利だったとの報告があります。Cureus 15, e42491 (2023).
「夕食後1日1回」のテオフィリンを朝食後に変更することで、夜間の尿量増加が抑制され、睡眠も改善する可能性があります。しかし、夜間~早朝の気道収縮に対する効果が減弱する恐れもあるため、注意が必要です。臨床現場では、朝200mg・夕200mgの分割投与も選択肢の一つかもしれません。
テオフィリン以外の治療への変更
テオフィリン以外の治療薬への切り替えも有効です。近年のCOPDや喘息治療ガイドラインでは、テオフィリンの位置づけは徐々に低下しています。これは治療域が狭く副作用リスクが高い一方で、より安全で有効な吸入薬が普及したためです。代替となる主な選択肢には、長時間作用型抗コリン薬(LAMA)や長時間作用型β₂刺激薬(LABA)、吸入ステロイド(ICS)などがあります。これらの薬剤は全身作用が少なく、テオフィリンのような利尿作用や中枢刺激作用による夜間頻尿を引き起こす可能性が低いのが特徴です。特に高齢者や合併症を持つ患者では、副作用の少ない治療選択が望ましいとされています。