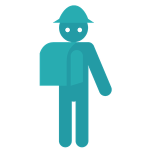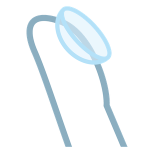【A】酸化マグネシウムと酸分泌抑制剤 (PPI・H2遮断薬)を併用することにより酸化マグネシウムの緩下作用が減弱すると考えられています。ただし、添付文書上では両薬剤とも併用禁忌や併用注意にも該当していません。そのため、便秘が改善しない患者に対してに限っては、PPI・H2遮断薬もしくは酸化マグネシウムの処方変更の一つになると考えられます。以下に詳細を記載します。
酸化マグネシウムの生体内における反応は
胃内 : 2HCl + MgO →MgCl2 +H2O
腸管内 : MgCl2 + 2NaHCO3 → 2NaCl + Mg(HCO3)2である。 生成物Mg(HCO3)2が腸管内の浸透圧を高めて腸内に水分を引き寄せることで排便を促すという機序です。。
しかし、酸分泌抑制剤を併用した場合は上記の反応がおこりにくく、 Mg(HCO3)2の生成が減少するため、酸化マグネシウムの作用が減弱することが予想されます。
酸化マグネシウム単独群と酸分泌抑制剤併用群の2群に分け、それぞれの排便状況を調査した報告
・酸分泌抑制剤併用群 (PPI・H2遮断薬) は酸化マグネシウム単独群に比べ、排便コントールに要した酸化マグネシウムの投与量が有意に多かった。
・併用群は他の下剤の追加が必要となるなど排便コントロールは不良となった。
・酸化マグネシウムと酸分泌抑制剤を併用している患者が排便コントロール不良の場合には、他の作用機序の異なる緩下剤の作用も検討する必要がある。
(中国労災病院医誌 vol23, 36-39, 2014)