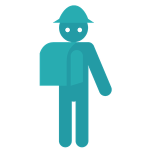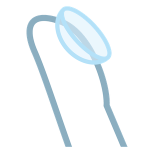【A】簡易懸濁法は基本的には、簡易懸濁後、長時間放置すると有効成分の分解や配合変化の恐れがあり、10分を超えて放置しないことが必要です。また、簡易懸濁法の配合変化は、注射薬の配合変化などと比較して、まだまだ十分な情報がありませんが、NaイオンやMgイオンは配合変化を起こしやすいため、塩化ナトリウム、酸化マグネシウム、マグミットなどは他の薬剤と同時に簡易懸濁法を行う際には注意が必要とされています。
錠剤を溶かすとアルカリ性溶液になり、配合変化に注意が必要な薬剤があります。例えば、酸化マグネシウムを懸濁すると、アルカリ性になります。他には以下の通り、不溶性キレートの生成や溶出性の遅延に注意が必要な薬剤があります。
1. 酸化マグネシウム+レボドパ製剤
マドパー配合錠やメネシット配合錠(レボドパ製剤)などは、アルカリ性下において酸化分解するため、酸化マグネシウムと懸濁すると、メラニンを生じ黒色となり、レボドパ製剤の効果が低下することがあります。また、同様にクラリスロマイシンDSやアジスロマイシンDS、リーマス錠も溶液をアルカリ化させるため注意が必要です。
2. 鉄製剤+レボドパ製剤
フェロミア錠などの鉄製剤はレボドパからメラニンへの酸化促進作用があり黒色化するため、注意が必要です。不溶性のキレートが形成されます。
3. 塩化ナトリウム+抗生物質
クラビット錠と塩化ナトリウムを簡易懸濁する場合は、クラビット錠を崩壊した後に塩化ナトリウムを入れると容易に崩壊しますが、逆の順序であれば崩壊が遅延してしまいます。オーグメンチン配合錠、ガチフロ錠、トミロン錠、フロモックス錠も同様です。塩化ナトリウム量が多いほど溶出が遅延してしまいます。
他には以下の薬剤に注意が必要です。
- ケーワン→アルカリに不安定
- コスパノン→アルカリに不安定
- ジキトキシン→アルカリに不安定
- アルドメット→酸・アルカリに不安定
- セルベックス→強酸性下で分解
(参考 : 内服薬 経管投与ハンドブック 第3版, 月刊薬事. 48 : 723-730 2006 , 月刊薬事. 48 : 905-910 2006)