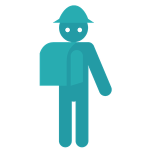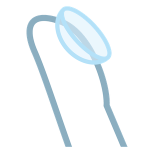保険適応外ですが、いくつかの三次除菌の方法が報告されています。。
三次除菌は「PPI+アモキシシリン1500mg+シタフロキサシン200mg」となります。 (J Gastroenterol.48 : 1128-1135, 2013)。シタフロキサシンの代わりにレボフロキサシンを使用することもあるが、耐性化が懸念されています。
以下の報告もされています。
プロトンポンプ阻害薬、
アモキシシリンまたはメトロニダゾール、 シタフロキサシンの3剤併用療法 例)ラベプラゾール10mg 1回1錠 1日4回 + アモキシシリン250mg 1回2CP 1日4回 + シタフロキサシン50mg 1回2錠 1日2回 7日間または14日間例)ラベプラゾール10mg 1回1錠 1日4回 + メトロニダゾール250mg 1回2錠 1日2回 + シタフロキサシン50mg 1回2錠 1日2回 7日間参考)H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2016改訂版Q&A
上記の (例) のラベプラゾール10mgを1回1錠 1日2回とする例もあります。ラベプラゾール10mgを1日2回投与するのか、1日4回投与するのかの判断は、患者のCYP2C19遺伝子多型が高速代謝型や中間代謝型 (1日4回)であるのか。低速代謝型(1日2回)であるのかが一つの目安となります。日本人のCYP2C19 代謝活性欠損者の頻度は約20%と多くなっており、考慮した投与回数とする必要があります。
また、ラベプラゾールをCYP2C19寄与度の低いネキシウム(エソメプラゾール)に変更することも可能です。
しかし、RCT論文によると、intention-to-treat(ITT)解析の除菌率はネキシウム(エソメプラゾール) 1回1錠1日2回の場合、ラベプラゾールと比較して大きく改善はされていませんでした。(同等もしくは低下)
参考)H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2016改訂版Q&