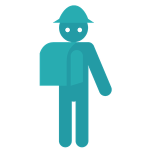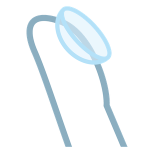【質問】ブロムワレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素が鎮痛補助剤として使われる場合の機序はどのようになっているのでしょうか?また、相互作用、注意点はありますか?
【A】「ブロムワレリル尿素」、「アリルイソプロピルアセチル尿素」の鎮痛補助に関連した作用機序は明らかとなっておりません。一方で、ブロムワレリル尿素の鎮静作用の作用機序については、明らかとなっています。「ブロムワレリル尿素」はBrが含有されているため、体内のCl-と置換されます。抑制性神経伝達物質のGABAやグリシンは細胞内外のCl-濃度と関連しているため、「ブロムワレリル尿素」のBrが体内のCl-と置換されることにより、鎮静効果が生じると考えられます。
以下の添付文書に記載されている内容からも、鎮静作用の面から鎮痛補助に対して効果があることが理解できます。
Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeuticsには「ブロムワレリル尿素」、「アリルイソプロピルアセチル尿素」に関する記載はありませんでした。米国ではこれらの成分の薬剤は使用されていません。
一方で国内においてOTCにも含有されているため、入手が容易であり、過量服薬による中毒に注意が必要と考えられます。
ブロムワレリル尿素「JG」
不眠症、不安緊張状態の鎮静血中に入るとBr‐を遊離し、体内のCl‐と置換する。中枢神経系で細胞膜輸送系を障害する脳脊髄中にも大量に移行して、大脳の興奮を抑制し、鎮静・催眠作用と抗痙攣作用を示す。作用の発現が早く、接続時間は短い。
(ブロムワレリル尿素「JG」添付文書)
→「ブロムワレリル尿素」の添付文書には不眠症、不安症状の鎮静作用と記載されています。
SG顆粒
解熱鎮痛成分の効果増強作用を持つ鎮静成分のアリルイソプロピルアセチル尿素の合計4種類の有効成分アリルイソプロピルアセチル尿素は穏和な鎮静薬で、痛みに伴う不安,不快感,恐怖心等の疼痛反応を除去することにより疼痛を緩和するとともに、鎮痛薬の作用を増強する
(SG顆粒 添付文書)
→痛みに伴う不安,不快感,恐怖心等の疼痛反応を除去することで疼痛を緩和すると明記されています。
配合剤による中毒の場合 [次に示す薬物とは相互作用によってアセトアミノフェンの毒性が強発現するとの報告がある。] ・エテンザミド ・無水カフェイン ・ブロムワレリル尿素
(アセチルシステイン内用液17.6% インタビューフォーム)
→作用機序は明記されていませんが、ブロムワレリル尿素を併用するとアセトアミノフェンの毒性が強発現する可能性があるため注意が必要です。また、アセトアミノフェンの鎮痛効果が増強するとも考えられます。
入手の容易さから、現在、ブロムワレリル尿素による中毒は,わが国の代表的な薬物中毒の一つである。(財)日本中毒情報センターへの問い合わせ件数は,2000年に76件1),2001年に70件2)、科学警察研究所資料3)による中毒死者数は,1999年に37人,2000年に42人(多剤同時摂取を含む)となっている.
1) (財)日本中毒情報センター:2000年受信報告.中毒研究 2001;14:145-64.
2) (財)日本中毒情報センター:2001年受信報告.中毒研究 2002;15:195-225.
3) 科学警察研究所:薬物による中毒事故等の発生状況,科警研資料第43報2001,第44報2002
(一般社団法人 日本中毒学会 http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no3/)
→米国ではすでに使用されておらず、日本においてはOTCなどで容易に入手できることから、過量服薬による中毒が注意点として挙げられます。